はじめに
大学受験は、あなたが思っているよりも早く訪れます。新高2生の皆さんは、まだ受験まで時間があると思っているかもしれませんが、実はこの1年間こそ、受験の成否を左右する重要な時期です。
高校2年生は、受験対策を本格的に始める最初のタイミングであり、今からしっかりと学習を進めることで、受験勉強を効率的に進めることができます。
この記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、新高2生が今から始めるべき受験対策や学習方法について解説します!受験勉強を始めるにあたって大切なポイントを押さえて、効率的に実力を伸ばすための戦略を一緒に見ていきましょう。
私は高校3年生になり受験直前となったタイミングで、「高校2年生のときにやっておけば・・・」と思ったことがいくつもありました・・・。みなさんはそのようにならないようにために、この記事を参考にしてください!
受験対策のスタートライン:新高2生に必要な準備
受験の全体像を把握する
まず、受験勉強を始める前に、大学受験の全体像を理解しておくことが重要です。受験には、さまざまな方式がありますが、特に押さえておくべきポイントは以下の通りです。
共通テスト
大学入学共通テスト(旧センター試験)は、全国で一斉に行われる試験で、多くの大学で必須となります。これに向けて、基礎的な学力をしっかり固めることが重要です。
二次試験(個別試験)
共通テストの後に、志望校が実施する二次試験があります。二次試験は、大学ごとに異なる内容が求められるため、早い段階で志望校の過去問を分析し、二次試験に備えた対策を考えましょう。
推薦入試・AO入試
一部の大学では、推薦入試やAO入試を実施しており、一般入試と異なる対策が必要です。これらを受ける予定がある場合、一般入試とは異なる準備が求められるため、早めに情報収集を行いましょう。
受験の全体像を把握することで、自分の受験方式や進むべき学習方向を明確にすることができます。特に、新高2生のうちは、全体像をしっかりと把握しておくことで、受験準備を効率よく進めることができるようになります。
志望校と目標を決める
受験の対策を始めるにあたって、志望校を決めることは非常に大切です。志望校が決まっていないと、学習のモチベーションが低下したり、無駄な努力をしてしまったりする可能性があります。
志望校を決める際のポイントは以下の通りです。
自分の得意科目と興味を考える
志望校を決める際に、まず自分の得意科目や興味を考えてみましょう。好きな科目であれば、学習のモチベーションも維持しやすくなります。また、将来進みたい分野に関連する学科を選ぶことも一つの方法です。
偏差値を考慮する
自分の現時点での学力を把握し、志望校の偏差値を考慮して目標を設定します。高すぎる目標を設定すると、挫折することがあるため、最初は自分の学力に見合った大学を目指し、少しずつレベルアップを目指すのが理想的です。
入試科目と方式を確認する
志望校を決めたら、次にその大学の入試科目や受験方式を確認しましょう。必要な科目が自分の得意分野かどうか、また推薦入試やAO入試の選択肢があるかも確認しておきます。
また私はオープンキャンパスなども高校2年生の時に行っていました。キャンパスの雰囲気なども志望校選びに重要かもしれませんね。志望校を明確にすることで、受験勉強が具体的になり、どの科目に力を入れるべきかが見えてきます。目標が定まることで、学習計画も立てやすくなり、効率的に勉強を進めることができます。
現在の学力を把握する
新高2生にとって、自分の学力を客観的に把握することは非常に重要です。
春の時点で、現在の自分の得意科目や苦手科目を把握しておくことで、今後の学習計画を立てやすくなります。
模試を受ける
定期的に模試を受けることで、自分の学力を数値で把握できます。模試の結果を見て、弱点を特定し、その部分に重点的に学習を進めることができます。
過去問を解く
志望校の過去問を早い段階で解くことで、試験の傾向や自分の弱点を知ることができます。過去問を解くことで、どの分野が得意で、どの分野が苦手なのかを確認できます。
これらの手段を使って、現在の学力を客観的に把握し、必要な対策を考えることが受験対策の第一歩となります。
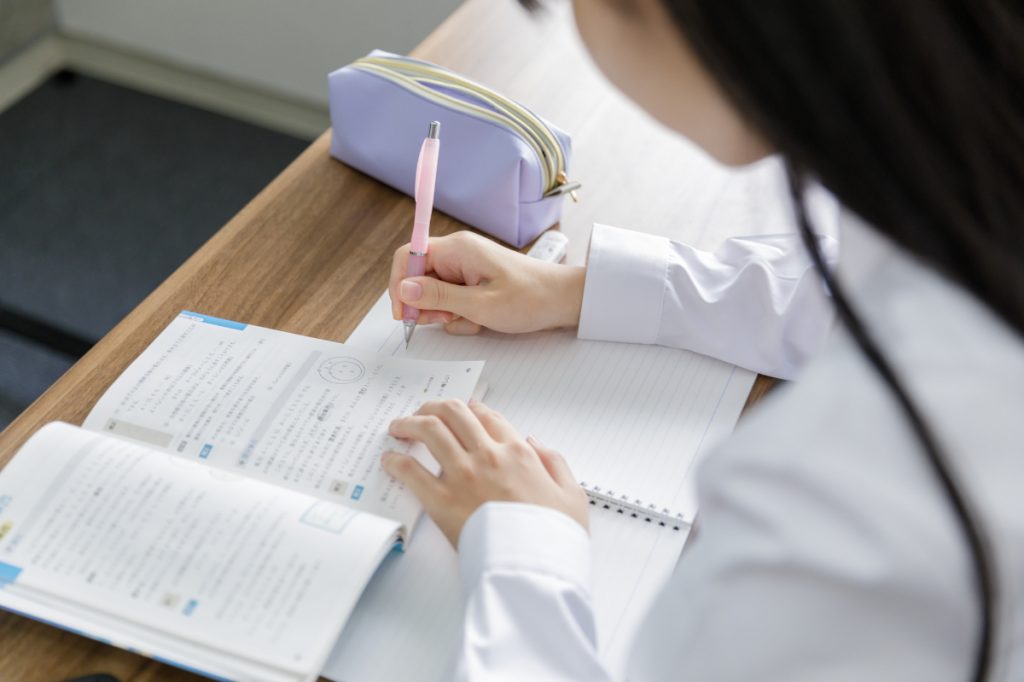
効率的な勉強法と学習計画
1日の学習スケジュールを立てる
受験勉強を効率的に進めるためには、計画的に学習することが重要です。毎日の勉強時間や学習内容をあらかじめ決めておくことで、無駄なく学習を進めることができます。
以下は、新高2生が実践すると良い1日の学習スケジュールの例です。
| 時間帯 | 学習内容 |
|---|---|
| 6:30 – 7:00 | 英単語・古文単語の暗記 |
| 8:00 – 16:00 | 学校の授業(しっかり聞く) |
| 17:00 – 19:00 | 予習・復習(学校の授業内容) |
| 19:00 – 21:00 | 受験対策(苦手科目の克服) |
| 21:30 – 22:00 | 共通テスト対策・問題演習 |
| 22:30 – 23:00 | 単語・知識系科目の暗記 |
自分の生活スタイルに合わせて、無理なく勉強を続けられるスケジュールを立てましょう。時間帯ごとに学習内容を分けて、効率的に学習を進めます。
科目別勉強法
受験勉強では、科目ごとに効果的な勉強法を取り入れることが重要です。それぞれの科目について、基本的な勉強法を解説します。
英語
- 毎日英単語を覚える
毎日少しずつ単語を覚えていくことで、語彙力を着実に向上させます。1日30語程度を目標に覚えると効果的です。 - 長文読解を強化する
共通テストや入試で出題される長文読解は、繰り返し練習することが大切です。過去問を使って、読解力を高めましょう。
数学
- 基礎問題を徹底的に解く
数学の基礎が固まっていないと、難しい問題に取り組んでも成果が出にくいです。基礎的な問題をしっかり解き、定着させましょう。 - 問題集を繰り返し解く
難易度の高い問題に挑戦する前に、問題集を何度も繰り返して解くことで、解法パターンを覚えることができます。
国語
- 毎日1題読む習慣をつける
現代文の読解力を高めるために、毎日1題の文章を読む習慣をつけましょう。
理科・社会
- 暗記と演習をバランスよく行う
暗記が必要な科目は、理解と記憶をしっかり定着させるために、定期的に復習を繰り返すことが重要です。
効率的な学習法とモチベーション維持のコツ
勉強の質を高める方法
受験勉強を効率的に進めるためには、単に勉強時間を増やすだけではなく、勉強の質を高めることが非常に重要です。以下の方法で、勉強の効率と質を高め、効果的に学習を進めていきましょう。
アクティブリコール(積極的に思い出す)
アクティブリコールとは、学習した内容を受動的に思い出すのではなく、積極的に自分の頭の中で引き出す勉強法です。例えば、教科書やノートを見ながらただ読んでいるだけではなく、問題を解いたり、自己テストを行うことで、記憶が強化されます。
積極的に思い出すことで、記憶が定着しやすくなるため、特に暗記科目や理解を深めたい分野に効果的です。
ポモドーロ・テクニック
ポモドーロ・テクニックは、集中と休憩を交互に繰り返す学習法で、効率的に勉強を進めることができます。
この方法では、25分間の集中学習後に5分の休憩を取り、これを繰り返します。集中している時間が短いため、集中力が持続しやすく、学習の効率が上がります。
また、休憩を取ることでリフレッシュし、次の学習に集中しやすくなるので、長時間の学習にも向いています。
勉強の記録をつける
勉強の進捗を記録することで、自分の努力がどれだけ積み重なっているのかを実感できます。
また、記録を見返すことで、達成感を感じることができ、モチベーションが維持されやすくなります。例えば、毎日勉強した内容をノートに書き出し、どの科目をどのくらいの時間学習したのかを把握することが重要です。
このような記録は、長期的に見て非常に有効です。
環境を整える
効率的な学習には静かな学習環境が不可欠です。勉強に集中できる場所を確保し、学習スペースに不要なものを置かないようにすることで、集中力を高めることができます。
また、机の上を整理整頓し、必要な教材や文房具だけを置くことも重要です。もし、自宅では集中できない場合は、図書館やカフェなど、集中しやすい環境を探してみるのも一つの手です。
休憩の質を高める
勉強における休憩も非常に重要です。適切な休憩を取ることで、集中力が回復し、学習効率が向上します。
休憩時間に軽いストレッチや深呼吸を取り入れることで、脳のリフレッシュができます。さらに、長時間勉強した後には、仮眠を取ることで疲れを軽減し、残りの学習時間を効率的に使うことができます。休憩の質を高めることで、疲れを感じにくく、勉強のパフォーマンスを維持できます。
モチベーションを維持する方法
受験勉強は長期間にわたるため、モチベーションを維持することが大きな課題となります。
モチベーションが低下すると、勉強を続けることが難しくなり、成果が上がりにくくなります。ここでは、モチベーションを維持するための具体的な方法をいくつか紹介します。
合格後の自分を想像する
受験勉強が長期戦であるため、モチベーションを保つためには、目の前の苦しい勉強を乗り越えるためのビジョンが必要です。合格後の自分を想像し、志望校で学ぶ姿を頭に浮かべることで、「この勉強が無駄ではなかった」という気持ちが芽生え、前向きに勉強を続けることができます。
また、将来の自分がどんな職業に就きたいか、そのためにはどんな大学に通いたいかをイメージすることで、受験勉強が意味のあるものに感じられます。
小さな目標を設定し、達成感を味わう
受験勉強を続けるためには、目標を細かく設定することが効果的です。
例えば、「今日中に英単語を50個覚える」「今週中に数学の基本問題を10回解く」など、具体的で達成可能な目標を設定します。目標を達成するたびに自己肯定感が高まり、勉強へのモチベーションが維持されます。小さな目標の達成を繰り返すことで、大きな目標に近づいている実感を得ることができ、モチベーションが持続しやすくなります。
同じ目標を持つ仲間と励まし合う
受験勉強は孤独な作業ですが、仲間と励まし合いながら進めることで、モチベーションを維持することができます。同じ目標を持つ仲間と情報を交換したり、勉強方法を共有したりすることで、刺激を受けることができます。
また、互いに成果を報告し合うことで、励まし合いながら勉強を進めることができ、勉強に対する意欲が高まります。
息抜きの時間を確保する
長時間勉強を続けていると、疲れやストレスが溜まり、集中力が低下します。
そのため、適度な息抜きの時間を確保することが重要です。例えば、週に一度は好きな映画を観る、友達と出かける、趣味に没頭するなど、リフレッシュの時間を作りましょう。これにより、精神的な疲れを取り除き、再び集中して学習に取り組むことができます。



受験対策のまとめ
受験対策は長期間にわたる戦いです。しかし、新高2生の今からしっかりと準備を進めることで、将来の大学受験に大きな差をつけることができます。以下のポイントを心掛けて、効果的な勉強とモチベーションの維持をしていきましょう。
受験対策は早期スタートが鍵
新高2生のうちは、まだ十分な時間があります。この時期に基礎力を固めることが最も重要です。無理に過度な勉強をするのではなく、計画的に基礎をしっかり固め、全体的な学力を底上げしましょう。
効率的な学習法を実践する
ただ勉強するだけでなく、勉強の質を高めるためにアクティブリコールやポモドーロ・テクニックを取り入れ、集中力を維持しましょう。また、勉強環境や休憩時間を工夫し、学習効率を最大化することが重要です。
モチベーションを高め、維持する方法を実践
受験は長期戦です。目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることがモチベーションを維持するポイントです。また、勉強の息抜きに趣味やリラックス時間を取り入れることで、精神的な疲れをリセットすることができます。
ライバルと差をつけるためのポイント
他の生徒が遊んでいる時や、勉強をおろそかにしている時にこそ、計画的に学習を進めることが大切です。早期に始めることで、ライバルと差をつけ、自信を持って受験に臨むことができるようになります。
最後に、精神的にも健康を保つ
勉強だけでなく、体調管理や心のケアも受験準備には欠かせません。規則正しい生活を心がけ、適度な運動やリラックス法を取り入れることで、精神的な健康を保ちながら勉強に集中できる環境を作りましょう。
受験は辛い時期もありますが、努力は必ず報われます。日々の積み重ねを大切にし、地道に進んでいけば、希望する大学に合格できるはずです。自分を信じて、ポジティブな気持ちで受験準備を進めてください。











