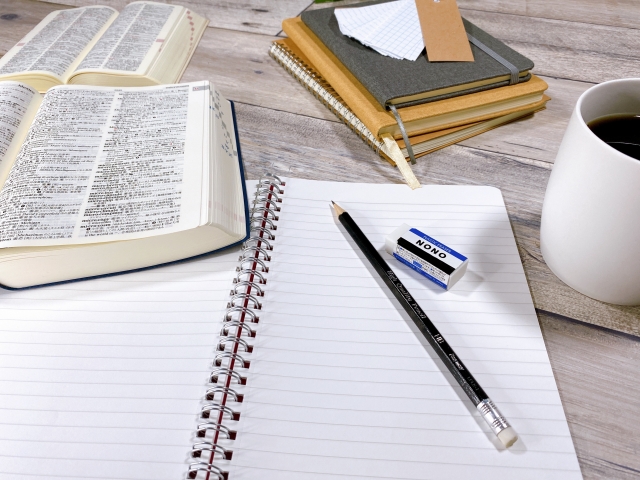はじめに
「復習って大事って言うけど、何をどうやってやればいいのか分からない…」
そんな風に感じたことはありませんか?勉強ができる人ほど、実は“予習よりも復習”を重視しています。
なぜなら、人間の脳は忘れるようにできているからです。どれだけ一生懸命勉強しても、復習をしなければ記憶はどんどん薄れていきます。せっかく理解した内容も、時間が経つにつれて「あれ、なんだったっけ?」と頭から抜け落ちてしまうのです。
一方で、正しいタイミングで、効果的な方法で復習をすれば、記憶は定着し、テストや受験本番でもしっかり使える知識になります。つまり、復習こそが勉強の成果を最大化する“カギ”なのです。
そこでこの記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、復習の重要性から、具体的なやり方、科目別のコツ、そして復習を習慣化するためのポイントまでしっかり解説します!
かくいう私も面倒くさいなと思い復習をサボってしまってた時期がありました・・・。しかし、復習をし始めてから暗記しやすく、理解が深まりテストの点数も上がり始めました!
ぜひ復習のやり方を見直したい方、これから学習習慣を整えたい中高生や保護者の方に、最後まで読んでいただきたい内容です。よろしければ参考にしてみてください!
復習の重要性とは?記憶のメカニズムを理解しよう
まずは、「なぜ復習が大切なのか?」という根本的な部分を理解しましょう。
私たちの脳は、一度学習した情報をすべて完璧に記憶できるわけではありません。心理学者エビングハウスの「忘却曲線」によれば、人は学習したことを1日経つと約70%忘れると言われています。つまり、「昨日完璧に覚えたはず!」と思っても、放っておけば翌日には半分以上が記憶から消えてしまっているのです。
ここで重要なのが“再入力”です。人間の脳は、繰り返し思い出すことで情報を長期記憶に移す仕組みになっています。
復習は、記憶を思い出すためのトレーニングであり、定着させるプロセスでもあります。言い換えれば、復習は「忘れないための勉強」です。これを意識するだけで、勉強の質が大きく変わります。
効果的な復習のタイミングと回数
復習の効果を最大化するには、「いつ」「どのくらい」やるかが重要です!次のタイミングを目安にすると、記憶の定着率が格段に上がります。
初回復習(当日)
授業が終わったその日のうちに、学んだ内容を振り返ります。軽くノートを見返したり、自分の言葉で要点をまとめたりするだけでもOK。この“即時復習”が、記憶の土台を作ります。
2回目(翌日)
翌日は忘却が進むタイミング。軽くテキストを見返しながら、覚えているかどうかをテスト感覚で確認します。ここでは、ただ読むのではなく、自分の頭でアウトプットすることがポイントです。
3回目(1週間後)
1週間経っても覚えていれば、記憶は強くなっています。逆に、忘れている部分があればこのタイミングでしっかり補強。演習問題に取り組むのも効果的です。
4回目(1か月後)
月末の振り返りとして、ノートをざっと確認する程度でOK。試験前にも役立つ、最終確認のような位置づけです。
このように、「スパンを空けた繰り返し」が復習のコツです!一気に詰め込むより、何度も分けてやる方が記憶はしっかり定着します。
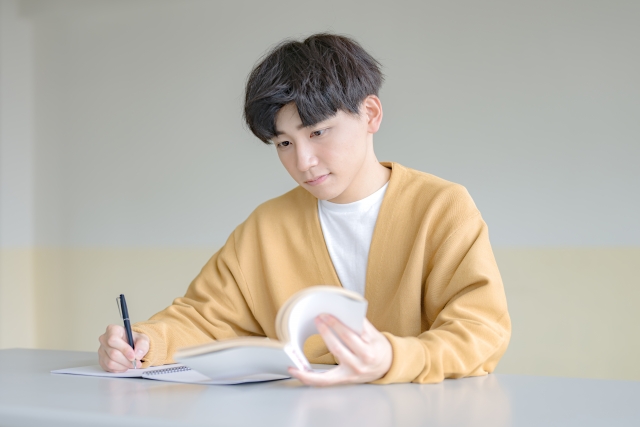
科目別:復習のやり方とコツ
科目ごとに適した復習方法を押さえておくと、効率よく学習を進められます。
英語
- 単語・熟語は、毎日5~10分ずつ反復
- 音読でリスニング力と理解力を同時に鍛える
- 文法は問題集で繰り返し演習
英語は“感覚”が大事なので、毎日少しずつ触れることが重要です。間違えた問題を「解き直す→音読→再確認」と多角的に復習すると効果的です。
数学
- 解き直しが復習の基本
- 間違えた問題には「なぜ間違えたのか」を必ず書き残す
- 解法を丸暗記ではなく、考え方の流れを理解する
解きっぱなしはNG。ミスの原因を分析し、「似た問題にどう応用するか」を考えることが本当の復習です。
国語
- 記述問題は添削を見直し、自分の書いた文章を客観視する
- 古文・漢文は文法と単語を反復
国語の復習は“答え合わせ”よりも“読み返し”がカギ!なぜその選択肢が正解なのかを文章中の根拠から説明できるようにすることが大切です。
理科・社会
- インプット→問題演習→見直し のサイクルが基本
- 図表・年表・用語カードを活用し、視覚的に復習する
- 問題集の「間違えたところリスト」を作る
暗記科目は、「何度も見て、使って、思い出す」ことがポイントです。自作のクイズ形式や、友達と出題し合うのもおすすめです。
復習を習慣化する5つの工夫
私は復習が面倒で、当日の復習をやらずに寝てしまう、なんてことが多々ありました・・・。そのようなことを防ぐメソッドをご紹介します!
学習スケジュールに「復習時間」を組み込む
予習や宿題だけでなく、「復習タイム」を明確にスケジュール化しましょう。30分でも復習専用の時間を確保するだけで、自然と習慣になります。
また、予習についてお困りの方はこちらの記事を参考にしてみてください!
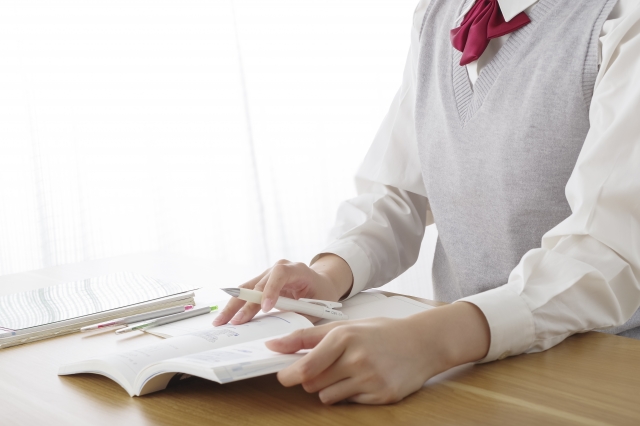
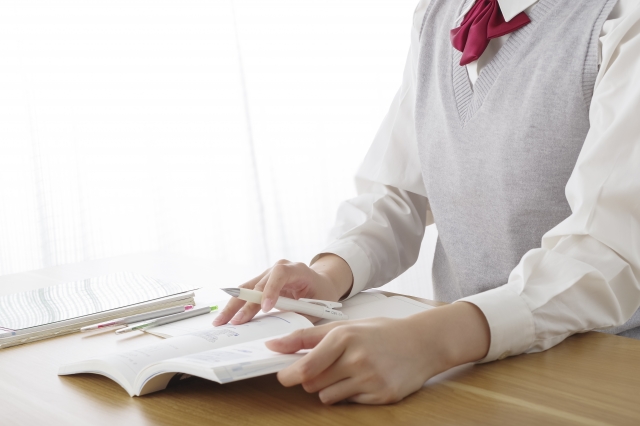
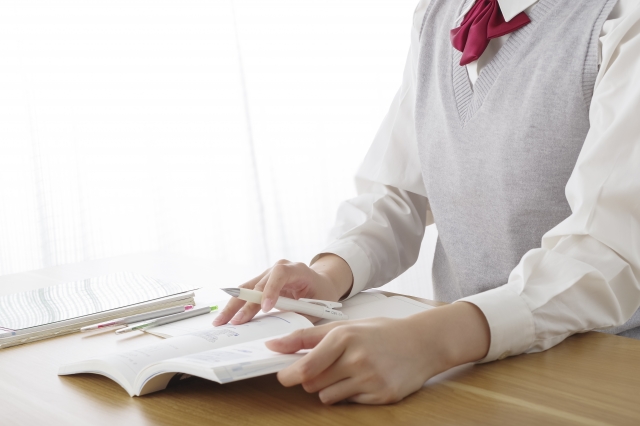
勉強ノートを“復習ノート”にする
その日の授業の要点、間違えた問題、気づきなどを1冊のノートにまとめておくと、後で見返すときに便利。復習ノートは“自分だけの参考書”になります。
忘れる前に軽く見返す
本格的な復習じゃなくても、教科書をパラパラ見るだけでも意味があります。「思い出す」という行為が記憶の定着を促します。
アウトプット型の復習を意識する
ノートを読んで終わり、ではなく、自分で説明したり、問題を解いたりする“アウトプット”を中心に復習するのが鉄則です。黙読よりも「話す」「書く」が効きます。
続けるための仕組みをつくる
チェックリスト、タイマー勉強法、ごほうび学習など、モチベーションを保つための仕組みを取り入れると継続しやすくなります。
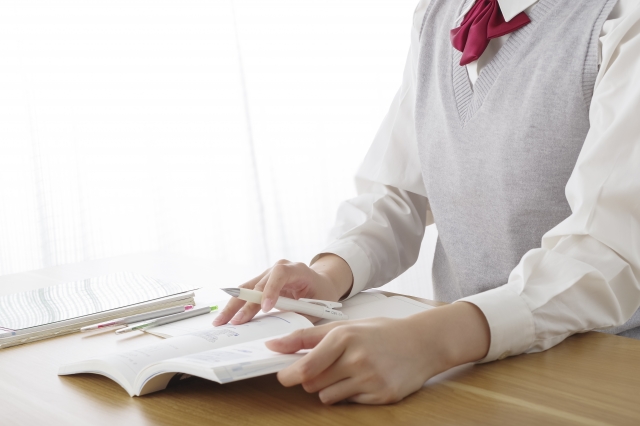
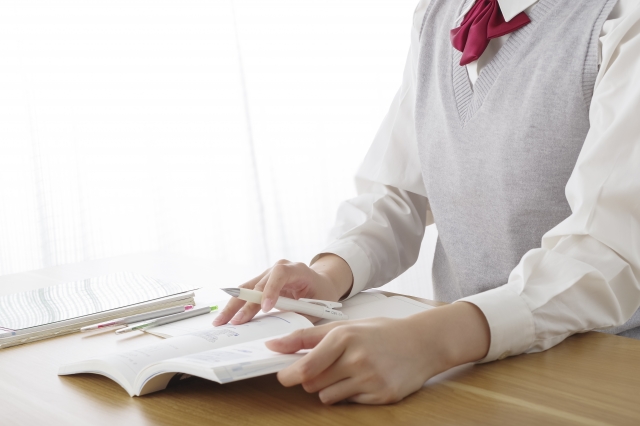
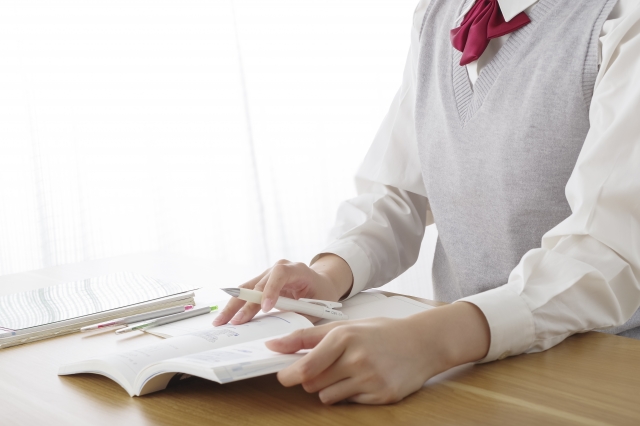
復習ノートの作り方と活用法
復習の効果を高めるためには、「ただ参考書を読む」「問題を解き直す」だけでは不十分なこともあります。そこでおすすめしたいのが、自分専用の「復習ノート」を作ることです。
このノートは、自分がつまずいたポイントや気づき、理解しきれなかった部分などをまとめておく“思考の記録帳”です。正しい作り方と活用法を知れば、勉強の効率を一気に高めることができます。
まず、復習ノートは市販のノートでOKです。ルーズリーフでもスケッチブックでも、自分が書きやすい形式で構いません。ノートを科目別に分けるのも良いですし、1冊にすべてをまとめておくのも後で振り返る際に便利です。
書き方のポイントは以下の3つです。
間違えた問題・不明点を中心に書く
復習ノートは「できたこと」を書く場所ではなく、「できなかったこと」「分からなかったこと」をまとめるためのものです。
間違えた問題をそのまま書き写すのではなく、「なぜ間違えたか」「何を勘違いしたのか」「次はどうすれば解けるか」といった“原因と対策”を書き添えることで、再発防止に役立ちます。
簡潔に、でも自分の言葉でまとめる
教科書や参考書の文章を丸写しするのではなく、自分の言葉で簡潔にまとめましょう。理解した内容を一度頭の中でかみ砕いて、言語化することが理解の定着につながります。図解やフローチャートを使うのも効果的です。
定期的に見返せるように工夫する
ノートは書くだけでは意味がありません。週に1回、月に1回などのペースで見返す時間を作りましょう。また、重要度に応じて色分けしたり、付箋でページを分類することで、必要な情報にすぐアクセスできるようになります。
このような復習ノートを継続して作成・活用することで、自分だけの「弱点リスト」や「ミス傾向の分析資料」が完成します。模試前や定期テスト前にも、これさえ見返せば“最短で自分の穴を埋められる”という信頼できる武器になるのです。
まとめ
復習は、「できるようになる」ための最後の一押しです。ただ授業を受けたり、問題を解いたりするだけでは本当の学力は身につきません。復習を通じて、知識を整理し、自分の中に落とし込むことで初めて“使える知識”になります。
復習を継続するには、完璧を求めすぎず、日々少しずつでも積み重ねることが大切です!忙しくても、たとえ10分でも復習に時間を使えば、その効果は確実に積み上がっていきます。
「忘れないために、思い出す」
これが復習の本質です。今日から、あなたの学習の中に“復習”という大きな武器を加えて、効率的に成績アップを目指しましょう!