共通テストのリスニングは、配点がリーディングと同じく100点満点になり、英語の総合得点に占める割合が大きくなっています。センター試験時代よりスピードも音声の種類も増え、短期間の対策では点数が安定しにくいのが特徴です・・・!
そこでこの記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、リスニングの傾向から効果的な勉強法、直前期の仕上げまでを詳しく解説します!
共通テスト・リスニングの出題傾向と特徴
共通テストのリスニングは、大きく以下の特徴があります。
- 1回しか流れない問題が多い(特に後半)
- 会話文・説明文・インフォメーションなど形式が多様
- イギリス英語・オーストラリア英語など、発音のバリエーションが増加
- 図や表を使って答える問題がある
- 日常的なやり取りから意見を述べる場面まで、内容の幅が広い
特に後半の大問5・6は、音声が一度しか流れず、かつ長めの会話や説明になるため、集中力と情報保持力が問われます!
効率的なリスニング対策のステップ
ステップ1:音声に慣れる
最初は「聞き取れなくてもOK」という気持ちで、毎日10〜15分、英語音声を聞く時間を確保します。教材は共通テスト過去問や模試の音声に加え、NHKラジオ英会話やBBC Learning Englishなどもおすすめです!
ステップ2:スクリプト確認と精聴
聞き取れなかった箇所はスクリプトを見て確認し、発音や単語のつながりを分析します。特に以下の3つを意識しましょう。
- リンキング(単語同士の音のつながり)
- 弱形(機能語の弱い発音)
- イントネーション(文の抑揚)
ステップ3:シャドーイング
スクリプトを見ずに音声の後を追うように発話する「シャドーイング」は、耳と口を同時に鍛えます。1日5分でも継続すると、聞き取れる音の幅が広がるのを実感できます。
ステップ4:設問先読みの習慣化
本番形式の演習では、音声が流れる前に設問と選択肢を先読みし、何を聞き取ればいいのかを明確にします。こうすることで、情報の取捨選択がスムーズになり、不要な部分に意識を奪われにくくなります!
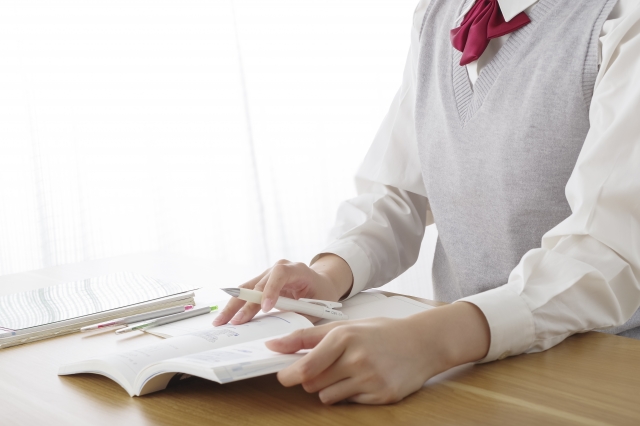
実戦練習と本番でのポイント
- 過去問演習
最低でも3年分は、本番同様の環境(時間・音声機器・一発勝負)で解きます。 - 集中力の維持
大問1〜6まで一気に解く集中力が必要です。普段の練習でも、通しで解く日を作りましょう。 - メモの取り方を統一する
メモは単語や数字だけに絞り、書きすぎないこと。書きながら聞くことはできません。 - 聞き逃しても気持ちを切り替える
一部を聞き逃しても、残りの情報で答えを導くことが可能です。焦らず次に集中しましょう。
リスニング力を伸ばすための長期的戦略
リスニングは短期詰め込みでは伸びにくく、**「耳の慣れ」**が必要な分野です。そのため、最低でも3〜6か月単位での計画が効果的です。ここでは長期的にスコアを伸ばすための戦略を解説します。
毎日の「英語のシャワー」
机に向かった勉強だけでなく、日常生活のスキマ時間に英語を流す習慣を持ちましょう。通学・通塾の電車やバス、家事中などに英語音声をかけ流します。聞き取れなくてもOKで、まずは英語の音・リズムを脳に染み込ませることが目的です。
精聴と多聴のバランス
- 精聴(1つの音声を繰り返し聞き、細部まで理解)
→ 発音や文構造の分析に向いており、弱点の特定に有効 - 多聴(多くの音声を広く聞く)
→ 語彙や表現の定着、リスニング耐性の向上に有効
両者を組み合わせることで、単調な学習にならず、理解とスピードの両立が可能になります。
「耳で覚える」単語学習
リスニングの弱点は単語力不足であることが多いです。紙の単語帳だけでなく、音声付きアプリやCDを使い、目と耳の両方から覚える習慣をつけましょう。特に機能語(前置詞・代名詞・助動詞など)の弱形は、耳から覚えたほうが本番で聞き取れやすくなります。
長期戦略のスケジュール例
- 4〜6か月前:多聴メインで耳慣らし、精聴で基礎固め
- 2〜3か月前:過去問や模試で実戦演習、先読み練習
- 直前1か月:本番同様の環境で通し練習+弱点補強
このように段階を踏んで取り組むことで、リスニング力は着実に向上します。
本番直前期に効果を発揮するリスニング強化法
試験直前の1〜2か月は、新しい教材に手を出すより、これまで使ってきた教材を繰り返し使うほうが効果的です。この時期に必要なのは「耳を慣らし切ること」と「解き方を完全に体に染み込ませること」です。
過去問音声の繰り返し練習
共通テスト本試験・予想問題集・模試の音声を使い、最低3回は解き直します。1回目は普通に解き、2回目はスクリプトを見ながら精聴、3回目はスクリプトなしで再挑戦します。この繰り返しで、聞き逃しやすい箇所が減ります。
「一度だけ聞く」練習
本番では後半問題は1回しか流れません。そのため、普段から**「一発勝負で解く練習」**を取り入れる必要があります。練習時も、聞き逃しても止めないで次に進むクセをつけましょう。
コンディション調整
リスニングは集中力が命です。試験時間に合わせて演習を行い、脳と耳をその時間帯に最も冴えた状態にするのが理想です。また、耳が冷えていると集中力が落ちやすいので、冬場は試験会場に行く際に耳当てやマフラーで温めておくのも意外に効果的です。
試験直前1週間の過ごし方
- 毎日30分〜1時間は音声を聞く
- 先読み+解答の流れを徹底反復
- 生活リズムを本番時間に合わせる
- 新しい教材は使わない(不安を増やすだけ)
最後の1週間は「やってきたことを最大限発揮するための調整期間」と割り切ることで、余計な焦りを減らせます。
英語特有の音変化を攻略する
共通テストのリスニングで大きな壁になるのが、英語特有の音のつながり・省略・変化です。単語一つひとつは知っていても、実際の音声ではまるで別物に聞こえることがあります。これを知らないまま本番を迎えると、「知っているのに聞き取れない」現象が頻発します。
リンキング(音のつなぎ)
例:get up →「ゲラップ」のように聞こえる
単語と単語の境目が消え、1つの塊として発音されます。この現象を意識すると、文章全体の流れをつかみやすくなります。
リダクション(弱化・省略)
例:want to →「ワナ」や「ワントゥ」
助動詞や前置詞など、強調されない単語が弱く短くなります。特に「a」「the」「of」などの機能語は音が極端に短くなるので要注意です。
フラッピング(tの弾音化)
例:water →「ワラー」
アメリカ英語でよく見られます。tが「ラ」に近い音になるため、tを意識しすぎると聞き取れなくなります。
対策方法
- ネイティブ音声をスクリプトと照らし合わせて聞く
- 知らない単語ではなく「知っているはずの単語が聞こえない箇所」を分析
- シャドーイングで発音を真似する(耳と口を連動させる)
音変化を知識として覚えるだけでなく、自分で発音できるようにすることで、脳が「音→意味変換」を高速化します。
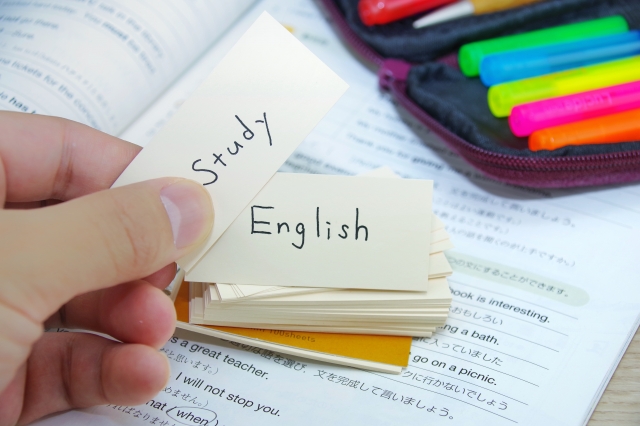
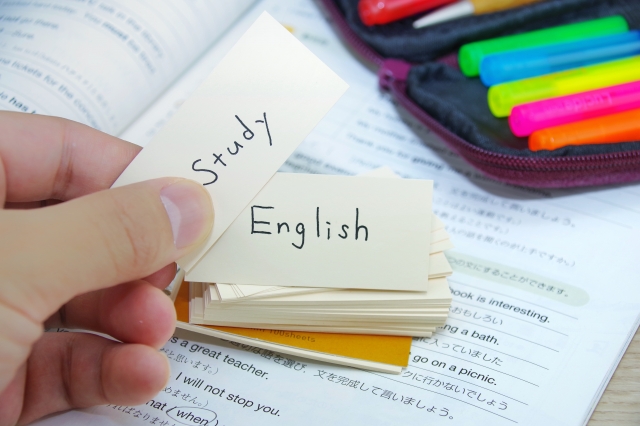
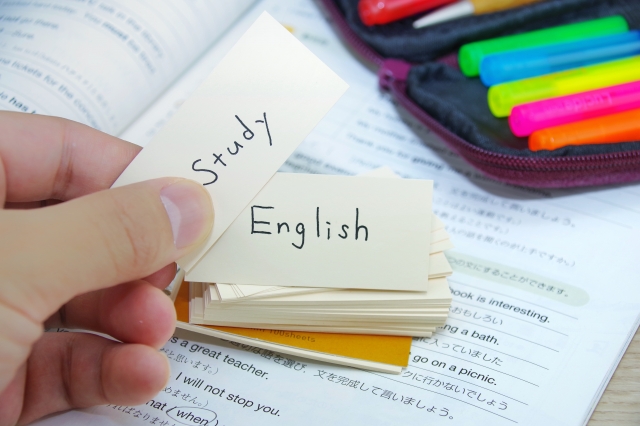
問題形式ごとの必勝アプローチ
共通テストリスニングは、出題形式が大きく3パターンに分かれます。形式ごとの特徴と対策を押さえることで、同じ英語力でも得点効率を上げることが可能です。
短文理解(前半)
比較的シンプルなやり取りや描写が多く、英語の処理スピードよりも「集中力と丁寧さ」が求められます。
ポイント
- 選択肢を先読みして、何に注目すべきか明確化
- 数字や色、曜日などの具体情報に敏感になる
- 聞き取った情報を即座にイメージ化する
会話文(中盤)
2人以上の人物のやり取りで、話題が変わることがあります。
ポイント
- 誰が話しているのかを意識する
- 話の目的(依頼・提案・謝罪など)を早く把握
- 感情や態度を示す表現に注目(e.g., “That’s a good idea.”)
長文リスニング(後半)
1回読みの長文や講義形式など、情報量の多さと集中力の持続が課題になります。
ポイント
- 構成(導入→展開→結論)を意識してメモ
- メモは日本語でも英語でもOK、ただし省略形で
- 細部より全体像をつかむ意識を持つ
実戦練習のすすめ
形式ごとに分けた演習を週単位で行い、最後に通しで解く流れを作ると、効率的に得点力がアップします。過去問・予想問題集・模試を活用し、解く→分析→改善のサイクルを短期間で回すことが重要です。
まとめ
共通テストのリスニングは、リーディングと同じ配点でありながら、多くの受験生が軽視しがちな分野です。しかし、正しいトレーニングを数ヶ月継続すれば、短期間でも大幅な伸びが期待できます。
音声に毎日触れる環境を作り、設問先読みやシャドーイングなどのテクニックを習慣化することが、高得点への最短ルートです!
また自習での対策に不安がある方はぜひ東大寺子屋を活用してください!現役東大生の講師陣があなたのレベルに合わせリスニング能力の向上をお手伝いします。興味がある方はまずお気軽にお問い合わせください!











