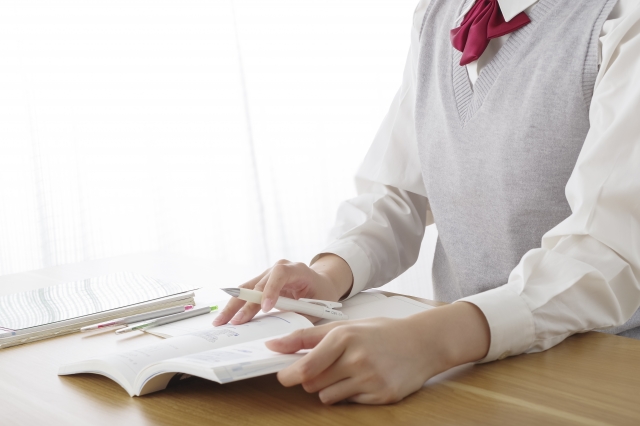はじめに:同じテストなのに意味が違う!?
「共通テスト」と聞くと、「受験生全員が受ける全国共通の試験」として一括りにされがちですが、実は国立大学と私立大学では、その意味も、影響力も、まったく異なります。
同じテストを受けていても、
- 「国立志望」なら共通テストの点数で出願校が左右される
- 「私立志望」なら共通テストを使わない方式(一般入試)も多い
というように、受験戦略の中での「共通テストの立ち位置」が違うのです!
そこでこの記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、国立・私立それぞれにおける共通テストの役割、戦略的な活用法、そして科目ごとの注意点までを詳しく解説していきます!
国立大学における共通テストの位置づけ
共通テスト=出願可能な大学を決める「第一関門」
国立大学を受験する場合、共通テストはほぼすべての大学・学部で課される必須試験です!
センター試験時代と同様、共通テストの得点は「共通テスト利用方式の合否」だけでなく、2次試験に進むための“足切り”や配点の一部にも使われます。
特に地方国公立や中堅大学では、共通テストの比重が高く、7〜9割の得点が必要になることも。
一方で、東京大学や京都大学のような難関国立では共通テストよりも2次試験が重視されるため、6〜7割確保できれば十分合格圏内ということもあります。
科目数が多い=バランス型の学力が問われる
国立大学では、文系理系問わず基本的に5教科7科目を受験することが前提です!
- 文系:英語・国語・数学ⅠAⅡB・地歴公民・理科1科目
- 理系:英語・数学ⅠAⅡB・理科2科目・国語・地歴公民(1科目)
このように、国立志望者は主要科目に加えて、理社も満遍なく対策が必要になります。
特定の科目が苦手でも、その分他の科目でカバーしないといけないというプレッシャーがあります。つまり、得意不得意を極端に分けすぎると失敗しやすいという特徴があるのです。
私立大学における共通テストの位置づけ
共通テストは“使わない”という選択肢もある
私立大学の受験では、共通テストを使う方式と使わない方式の両方が存在します。
- 【一般入試】:大学独自の問題を使った筆記試験(最もポピュラー)
- 【共通テスト利用方式】:共通テストの得点を出願に用いる(大学によって配点が異なる)
- 【併用方式】:共通テスト+独自試験の合計得点で判定
たとえば、早稲田大学や上智大学などの難関私立でも、共通テストを一切使わずに合格できるルートがある一方で、明治・中央・法政などのMARCHグループでは、共通テスト利用方式を積極的に活用しています。
つまり、私立志望者にとって共通テストは「受けてもいいし、受けなくてもいい」もの。
戦略次第で大きなチャンスにもなるし、重荷にもなり得ます!
「高得点勝負」で、1点が命取り
私立大学の共通テスト利用方式は、多くの場合「3〜4科目」での合否判定となり、得点率が9割前後でないと合格が難しいというハイレベルな戦いになります・・・!
- 英語・国語・世界史で90%超え→合格
- 英語・国語・数学で平均85%→厳しい
というように、受験者の平均レベルが非常に高いため、共通テストでの「上位数%」に入ることが前提になるのです。
また、独自試験よりも受験の負担が軽くなるという理由で、共通テスト利用方式を「滑り止め」として活用する受験生も多く見られます。

共通テストの英語:リスニングとリーディングの配点に注意!
2021年からスタートした大学入学共通テストでは、英語が「リーディング100点」「リスニング100点」と完全に分かれた形式になりました。
- センター試験時代:リスニング50点、リーディング200点
- 共通テスト:両方100点ずつ、配点比率50:50
これにより、リスニング対策を怠ると、配点の半分を失うという非常に厳しい試験になっています。
特に国立大志望者にとっては、英語全体の得点が安定しないと志望校を変えざるを得ない事態にもなりかねません。
一方、私立大学では英語の独自試験が主流で、リスニングを含まない大学も多いため、共通テストの英語が使われるかどうかは事前にしっかり確認しておきましょう!
共通テスト対策、いつから始めるべき?
共通テストの本番は1月中旬。高校3年生の1年間は驚くほどあっという間に過ぎていきます。
そのため、受験勉強のスタート段階から「共通テスト対策の意識」を持っておくことが、後の仕上がりに大きく影響します。
具体的には、高校3年生の夏休みまでに各教科の基礎を完成させることが理想です。夏以降は、共通テスト形式の演習と志望校別の個別対策を並行して進める必要があるからです。
- 4〜6月:インプット中心。教科書・基本問題の復習
- 7〜8月:共通テスト模試の形式に慣れる。苦手科目の洗い出し
- 9〜11月:時間を計った実戦演習。得点安定化を目指す
- 12月〜1月:過去問・予想問題で最終調整+弱点補強
このように「共通テスト専用の演習期間」を設けるには、基礎の完成と切り替えタイミングが鍵となります。
数学対策:処理力×読解力が試される
共通テストの数学は、センター試験よりも設問が複雑化し、文章・会話形式の問題が多くなりました。
そのため、単なる公式の暗記や機械的な計算だけでは歯が立たない構成になっています。
共通テストで求められるのは、**「問題の意図を読み取って手を動かす力」**です。つまり、数学力と読解力のハイブリッドが要求されるのです。
具体的な対策としては:
- 教科書の例題や基本問題で「型」を固める
- 教材は共通テスト対応の模試・予想問題を使う
- 問題文を丁寧に読む習慣をつける(会話文や図表に注目)
- 過去問演習では“時間配分”を意識する
また、特に数学I・Aではミスによる失点が合否を左右するため、正確さとスピードのバランスも重要です。
国語対策:現代文+古文+漢文、それぞれの型を押さえる
共通テストの国語は「情報処理力」を問う問題が増加しています。設問文が長く、選択肢の微妙な違いを見抜く力が必要になります。特に現代文では、文章の構造を読み解く力(要約力)が試される場面が多くなっています。
古文・漢文については、文法・語彙・句形のインプットを怠ると失点がかさむ分野です。共通テストでは設問自体はオーソドックスなため、基礎知識をしっかり入れておけば得点源にできます!
対策のコツは:
- 古文単語と敬語のパターンを短期集中で覚える
- 漢文句法と重要漢字は音読と演習で定着させる
- 過去問を通じて設問形式に慣れておく(時間配分の練習も)
- 複数の情報を整理する「線引き」「メモ書き」の習慣をつける
理社対策:アウトプット中心、暗記科目は“繰り返し”が命
理科・社会は、「一度覚えたら終わり」ではありません。共通テストで求められるのは、単なる知識ではなく「知識を使って考える」力です。
たとえば:
- 地歴では資料読み取り・地図との照合・因果関係の把握
- 倫理・政経ではグラフや統計資料と選択肢の照合
- 物理・化学では基本法則+日常的な現象の応用問題
- 生物ではグラフや図からの情報読み取りが中心
理社は、1日10〜15分でもいいので「毎日触れる」ことが重要です。繰り返しこそが記憶の定着に直結します。
また、共通テストの特徴として、設問の形式に慣れていないと失点する傾向もあるため、予想問題・模試を定期的に取り入れることが非常に効果的です!
苦手科目の伸ばし方:演習の“質”を見直す
共通テストでは「全体のバランス」が問われるため、1科目の苦手が足を引っ張るリスクが高いです。だからこそ、苦手科目の克服は最優先の課題です。
克服の第一歩は、「なぜ解けないか」を明確にすること。
- 問題の読み違いなのか?
- 知識不足なのか?
- ケアレスミスが多いのか?
原因が分かれば、対策も明確になります。
さらに、苦手科目は「やらされ勉強」になりやすいので、“小さな成功体験”を積み上げることが効果的です。
- 1問解けたら大きく丸をつける
- 正答率が上がったら日付と点数を記録する
- ストップウォッチで解く時間を測って「成長」を感じる
こうした小さな工夫の積み重ねが、勉強へのモチベーションを維持し、着実に成果につながります。



まとめ:共通テストは“賢く”向き合えば怖くない!
共通テストは、確かに出題範囲が広く、科目数も多く、形式も独特で不安になりがちです。
ですが、正しいタイミングで、正しい方法で向き合えば、得点力は確実に伸びていきます。
特に国立大学を目指す人は、共通テストが出願・判定に直結します。
私立志望者にとっても、使い方次第では大きなチャンスを得られる武器になります。
焦らず、計画的に、そして柔軟に。
共通テストを“敵”ではなく“味方”にできるかどうかが、受験の勝負どころです。
また、「何から始めればいいか分からない」「苦手が多くて不安」
そんなあなたに、東大寺子屋は共通テスト攻略の“道しるべ”になります!
志望校・成績・性格に合わせたカリキュラムで、
共通テストを「最大限に活かす」学習を一緒に設計してみませんか?興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください!