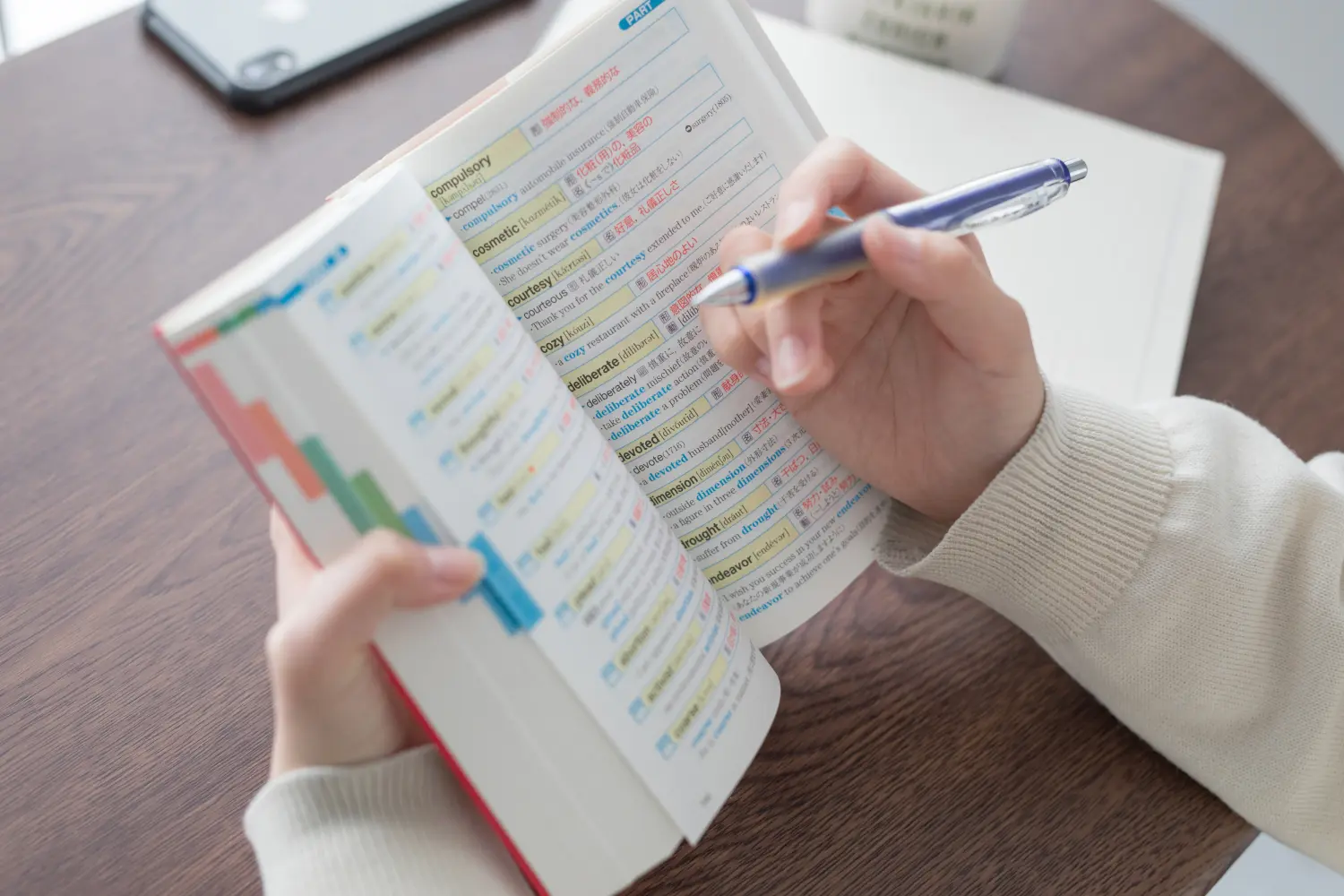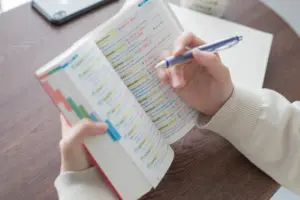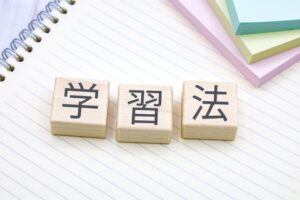はじめに
「参考書ってたくさんありすぎて、どれを選べばいいかわからない…」
そんな悩みを持っている中高生や受験生は多いのではないでしょうか?書店の棚にはずらりと並ぶ参考書たち。ネットでも「おすすめ参考書ランキング」や「○○高校合格者が使った参考書」など、情報があふれています。
でも本当に大事なのは“自分に合った参考書を選ぶこと”。
そこでこの記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、「参考書の選び方」について、目的別・科目別・レベル別に詳しく解説していきます!
かくいう私も、背伸びして『鉄壁』という高難度の英単語帳を使用していたのですが、暗記が苦手な僕には『シス単』などの単語帳の方が自分に合っていたな、という後悔もあります・・・。
みなさんは勉強の効率を最大限に高め、成績アップや志望校合格へとつなげるために、ぜひ自分にぴったりの一冊を見つけてください!
なぜ参考書選びが重要なのか?
勉強を始めるうえで、参考書は「道しるべ」のようなものです。間違った道を選べば、どれだけ努力しても目的地にはたどり着けません!
つまり、参考書選びを間違えると、どんなに一生懸命勉強しても、時間ばかりかかって成果が出にくいのです。
逆に、自分に合った参考書を選べば、同じ勉強時間でも理解度が上がり、定着力も強くなります。「この一冊を繰り返したら、苦手だった英語が得意になった!」という成功体験を持っている人は少なくありません。
参考書選びでまず意識すべき3つのポイント
自分の学力レベルを正確に把握する
今の自分の学力に合っていない参考書を使うと、内容が難しすぎて理解できなかったり、逆に簡単すぎて物足りなかったりします。
模試や定期テストの結果を参考にしつつ、「基本からやり直したいのか」「応用問題を伸ばしたいのか」など、自分のニーズを明確にしましょう。
目的をはっきりさせる
「定期テスト対策」「受験対策」「苦手克服」など、何のためにその参考書を使うのかによって、選ぶべき本が変わります。
たとえば、教科書の補助として使いたいなら、学校のカリキュラムに沿ったタイプを。入試の演習をしたいなら、過去問や模試形式の問題集が向いています。
続けられるかどうかを重視する
参考書選びで見落とされがちなのが、「継続性」。
どんなに有名な参考書でも、レイアウトが読みにくかったり、説明が回りくどかったりすると、途中で投げ出してしまいがちです。パラパラと中身を見て、「自分が続けられそう」と思えるものを選ぶことが、実はとても重要です。

科目別に見る!おすすめ参考書の選び方
英語
- 単語帳:例文が豊富で、語源や派生語まで載っているタイプがおすすめ!自分が使いやすい音声付きのものだと、リスニング対策にもなる。
- 文法書:基礎が不安なら、中学レベルから丁寧に解説されているものを。応用力をつけたいなら問題演習型で。
- 長文読解:レベルに合った分量・難易度のものを。設問の解説が充実しているタイプが理解を深めやすい。
数学
- 教科書準拠型:定期テスト対策には、学校の進度に合わせたものが最適。
- 解法パターン集:入試対策としては、「このタイプの問題にはこう解く」という流れをつかめる本が◎。
- 問題集:基礎→標準→応用の3段階で難易度が分かれているものが取り組みやすい。
国語
- 現代文:読解の手順が明確に示されている本を。解説が「なぜその選択肢が正しいのか」を論理的に説明しているかが重要。
- 古文・漢文:文法や語句をイラストや図解でわかりやすくまとめた本だと初心者でも取り組みやすい。音読や暗唱用のCD付きの本も効果的。
理科・社会
- 図解系:理社は暗記要素が多いので、図や表を活用して視覚的に整理されたものが◎。
- 一問一答:用語暗記には一問一答が便利。ただし、理解も深めたいなら、解説付きの一問一答にしましょう。
- 実践問題集:用語を覚えたら、すぐに演習問題に取り組んで定着させる流れが効果的。
参考書の活用テクニック
参考書は「買って満足」してしまいがちですが、最も重要なのはどのように活用するかです!同じ参考書でも、使い方次第で結果が大きく変わります。ここでは、効果的な参考書の使い方を紹介します。
まず大前提として意識したいのが、「一冊を完璧に仕上げる」ということです。複数の参考書に手を出すと、内容が重複したり知識がバラバラになったりしてしまいがちです。
特に基礎を固めたい段階では、一冊を何度も繰り返し、内容を確実に身につけることが大切です。最低でも3周以上を目安に取り組むと、理解と定着が深まります。
次に、解説を読み込む姿勢も重要です!問題を解いたあと、正解・不正解だけで判断して解説を流し読みする人も多いですが、実はこの「解説をしっかり読む」ことこそが、学力向上の鍵です。解き方のプロセスや、なぜその選択肢が正解なのか、間違いはどこにあったのかなど、丁寧に確認して次に活かしましょう。
また、復習のタイミングを工夫することも効果的です。「エビングハウスの忘却曲線」によれば、人間は新しく学んだことを1日後には約70%忘れてしまうといわれています。だからこそ、復習は翌日・1週間後・1か月後というように、間隔を空けて繰り返すと定着率が高まります。
さらに、自分に合った方法を取り入れる工夫もおすすめです。例えば、間違えた問題にマーカーを引いておき、苦手なポイントだけを重点的にやり直す。解説部分に自分の言葉で補足を書き込む。あるいは、音読して耳から覚えるなど、記憶のタイプに応じた学習法を組み合わせると効果的です。
最後に、勉強の記録をつけるのも良い習慣です。いつどこまで進めたか、何周したか、どの問題でつまずいたかを記録しておくと、次の学習がスムーズになります。



よくある参考書選びの失敗パターン
参考書を選ぶ際、ついやってしまいがちな失敗パターンがあります!自分にとって最適な一冊を選ぶためには、これらを避けることが非常に大切です。以下に代表的なミスと、その対策を紹介します。
まず最も多いのが、「口コミだけで選んでしまう」ケースです。SNSやネット上では「この参考書だけで偏差値70に上がった!」など、魅力的な口コミが並んでいます。
しかし、それが自分にも合うとは限りません。その人の学力、学習背景、理解スタイルが違えば、参考書の効果も変わってきます。大切なのは、「自分の現在地と目標に合っているか」を基準に選ぶことです。
次にありがちな失敗が、「タイトルや見た目に惹かれて買ってしまう」ことです。
「最強の○○」「これ一冊で合格!」などのキャッチーな表紙に魅了されて、つい手に取ってしまうことがあります。しかし実際に中身を見ると、自分のレベルに合わなかったり、レイアウトが読みづらかったりすることも。必ず内容をしっかり確認してから購入しましょう。
また、「複数の参考書を同時進行する」というミスもあります。これは意欲がある人ほどやってしまいがちですが、結果としてどの本も中途半端になってしまい、知識が定着しづらくなります。特に基礎固めの段階では、一冊を徹底的にやり込むことが最も効率的です。
さらに、「難しすぎる参考書を選んでしまう」のも危険です!背伸びをしてレベルの高い本を選びたくなる気持ちはわかりますが、途中でついていけなくなり、モチベーションが下がってしまう原因になります。難しいと感じたら、まずは1ランク下のレベルから始めて、確実にステップアップしていくのが賢明です。
最後に、「参考書を買って満足してしまう」という落とし穴もあります・・・!
新しい参考書を手に入れると、それだけで達成感を覚えてしまい、結局ほとんど手をつけないまま本棚に眠ってしまう…という経験、ありませんか? 参考書は使ってこそ価値があるので、「まずは目次を読み、スケジュールを立てて実行する」という習慣をつけましょう。
これらの失敗パターンを避けて、自分の勉強スタイルと目標に合った参考書を選べれば、学習効率は格段にアップします。参考書選びは“最初の一歩”にして“最大の選択”。焦らず、じっくりと選びましょう。
まとめ:あなたの“相棒”になる一冊を見つけよう
参考書選びは、勉強の成否を大きく左右する重要なステップです。ただなんとなく選ぶのではなく、「自分の目的」「現在のレベル」「使いやすさ」を軸に、じっくり選びましょう。
そして、一度選んだ参考書は「この一冊を完璧にする」という気持ちで取り組むことが、成績アップの近道になります。
誰かにとっての“神参考書”が、あなたにとってもベストとは限りません!だからこそ、焦らず、自分のスタイルに合った「勉強の相棒」を見つけてください。それがあなたの勉強を支える最強の武器になります。