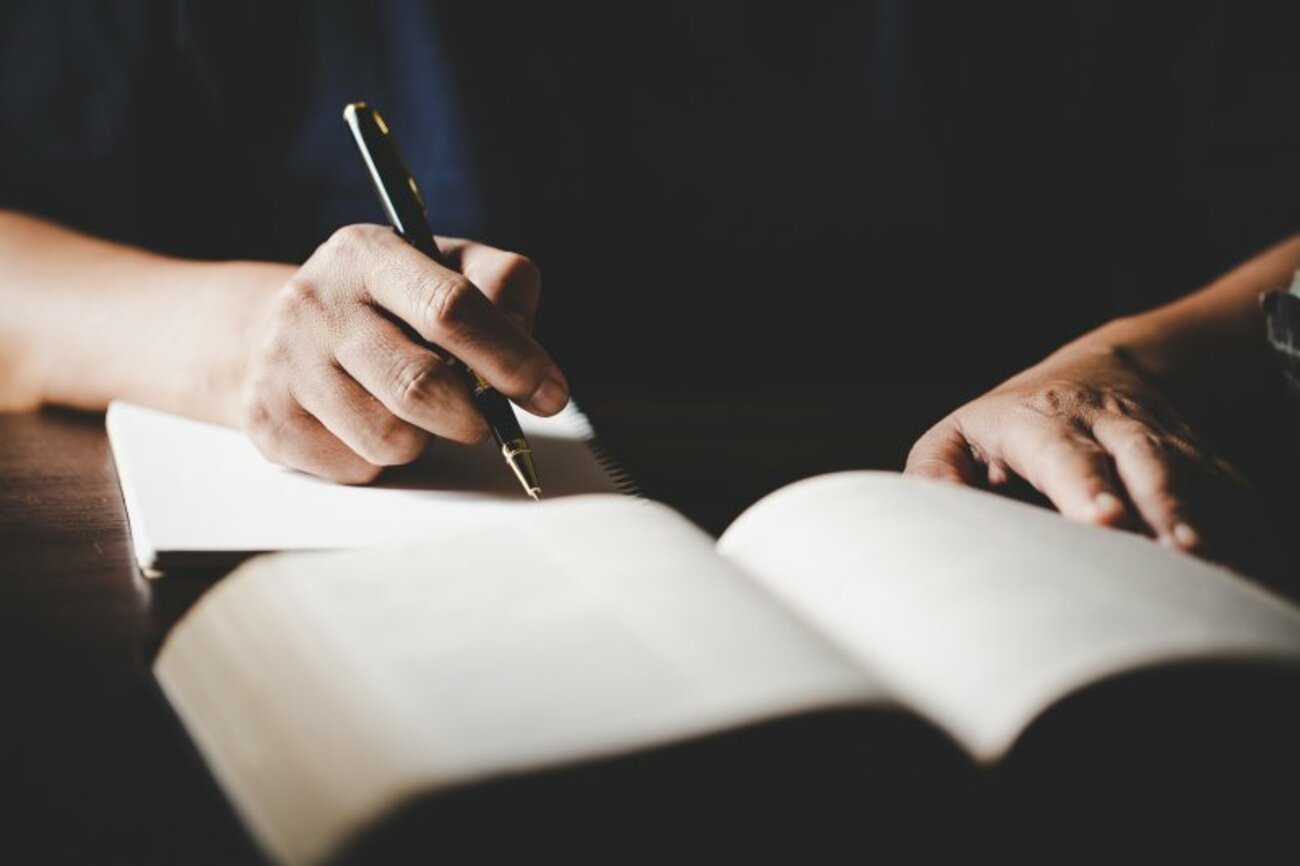文系だからといって理系科目に無関係…というのは、今や通用しません。
大学入学共通テストでは、文系志望であっても「数学」と「理科」の受験が必要になるケースが大多数です・・・!
特に国公立大学の文系学部では、共通テストで5教科7科目(国・英・数・理・社)が基本。私立大学でも共通テスト利用型入試を考えるなら、理系科目の対策は決して無視できない要素です。
では、文系受験生は共通テストで理系科目をどう選び、どう向き合うべきなのでしょうか?ここでは現役東大生ライターの「けんけん」が、選択科目の特徴やおすすめの対策法を解説します!
文系が受ける数学:I・Aが基本、II・Bも必要な大学あり
「文系なんだから、数学は関係ない」と思っていると、大学受験では思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
大学入学共通テストでは、文系学部を志望する生徒にも数学の受験が必須なケースが多いのです。
まず前提として、共通テストで文系が課される数学は以下のような構成です。
- 数学I・A(100点):全ての文系受験生が原則として受験する必須科目
- 数学II・B(100点):国公立大学の経済学部・教育学部・総合政策系など、一部で必要
つまり、文系志望でも数学を完全に避けて受験できるケースは非常に少数派で、特に国公立大志望なら、数学I・Aは“当たり前に”対策しなければなりません・・・!
文系生が数学を苦手とする理由とは?
数学を苦手とする文系生は多く、「数字を見るだけで拒絶反応が出る」という人も少なくありません。しかし、多くの場合、苦手意識の原因は「解き方がわからない」「何をやればいいか見えない」という“経験不足”にあります。
共通テストの数学I・Aは、決して難問ぞろいではありません。出題傾向も例年似ており、基本パターンを押さえておけば6〜7割は安定して取れる構成になっています。
出題されるのは以下のような定番分野です。
- 二次関数
- データの分析
- 図形と計量(余弦定理・正弦定理)
- 場合の数と確率
- 整数と不等式
- 数学的な論証
これらは、教科書+標準問題集(チャートやFocus Goldなど)を繰り返すことで着実に得点力が上がる分野です。
暗記ではなく、「考える訓練」に慣れることが得点アップのカギとなります。
数学II・Bが必要なケースもある
特に国公立大学の経済・経営・総合政策・教育系などの学部では、数学II・Bまで課される場合があります!
この場合、微分・積分・数列・ベクトルといった高校数学の後半部分も含まれるため、対策には一定の時間が必要です。
ただし、私立文系志望であれば、多くの大学で数学の受験は不要か、選択制となっています。
「どうしても数学が苦手」という人は、私立文系専願で国語・英語・社会の3科目に特化するという戦略も有効ですが、選択肢の幅を広げたいなら、やはり数学I・Aは“捨てずに”対策しておくのが安心です。

文系が選ぶ理科は「基礎2科目」or「専門1科目」
共通テストでは、文系生にも理科科目の受験が求められます。
「理系は物理と化学だけど、文系は何を選べばいいの?」と迷う人も多いでしょう。
実際、理科の選択には以下の2通りのパターンがあります。
■ 基礎2科目型(理科基礎×2):文系生の定番
文系のほとんどが選ぶのがこちら。
「理科基礎」とは、生物基礎・化学基礎・地学基礎・物理基礎の中から2科目を選んで、それぞれ50点ずつ(合計100点)受験するスタイルです。
もっともポピュラーな組み合わせは以下の通り:
- 生物基礎+化学基礎:暗記中心、計算少なめで文系向き
- 地学基礎+化学基礎:暗記量を分散しつつ、理解しやすい
この方式のメリットは、範囲が狭く、短期間で仕上げやすい点です。
また、基礎科目は共通テスト独自の出題形式があるため、過去問や模試で形式に慣れることで、得点が安定しやすい傾向にあります。
■ 専門1科目型(物理・化学・生物など):一部で必要
一部の国公立大学では、文系でも理科1科目(専門)を100点満点で課す方式を採用しています。
特に教育学部や医療系学部(看護・保健など)では、化学や生物の専門を要求することがあるため、要注意です・・・!
専門1科目の場合、範囲は広くなりますが、1科目に集中できるため得点を伸ばしやすいというメリットもあります。
ただし、完全独学で対応するのは難易度が高く、学校の授業や映像教材などを併用するのが望ましいでしょう。
文系生が理系科目を得点源に変えるための勉強法
理系科目に苦手意識を持っている文系生は多いですが、それだけに**「対策さえできれば周囲に差をつけやすい」**とも言えます。ここでは、文系が数学や理科を効率よく学ぶための勉強法を紹介します。
■ 数学I・Aは「パターン慣れ」と「時間管理」が鍵
共通テストの数学I・Aは、難問を解かせる試験ではありません。
むしろ「典型問題の応用力」と「時間配分」が問われる、スピードと正確性の勝負です。
【勉強法のポイント】
- 典型問題の演習を繰り返す
→ チャート式やFocus Gold、共通テスト対策用問題集で“頻出パターン”を体で覚える。 - 過去問演習は時間を測って行う
→ 「60分で何点取れるか」を常に意識することで、本番形式に慣れる。 - ミスノートを活用する
→ 自分が間違えた問題・パターンをまとめて復習。「同じミスをしない」意識を持つ。
文系生にありがちなのが、「1回解いてできた=OK」としてしまうこと。
ですが、数学の得点は“繰り返し”がモノを言う科目です。3回以上同じ問題を解くことで、パターンが脳に定着し、本番で焦らずに対応できます。
■ 数学II・Bは「絞って徹底」が有効
数学II・Bまで必要な人は、全範囲を中途半端に網羅するのではなく、頻出分野を重点的に鍛えることが効率的です。
頻出分野は以下の通り:
- 数列(漸化式・和の公式など)
- 微分・積分(最大・最小の応用)
- ベクトル(内積・図形との関係)
これらは毎年出題され、得点配分も高めです。基礎問題集で解法の型を固めたら、すぐに共通テスト形式の問題に移りましょう。
また、数学II・Bは数学I・Aよりも計算が煩雑なので、途中式の整理や図の活用が大切です。ノートにきれいに書くことよりも、「ミスを防げる書き方」を意識した練習を心がけましょう!



理科基礎の最短攻略法と注意点
理科基礎は、「とりあえず選んだけどよく分からない」という状態では得点できません。
実は、共通テストの理科基礎は一見簡単そうで、得点調整のために“思考問題”が仕込まれていることが多いため、表面の暗記だけでは点数が伸び悩むことがあります。
■ 生物基礎+化学基礎:暗記中心で取り組みやすい王道
- 生物基礎:体の仕組み・細胞・遺伝など。教科書レベルの知識+用語暗記が中心。
- 化学基礎:物質の性質・酸塩基・化学反応。計算もあるが、パターン練習で克服可能。
この2科目は**「わかりやすくて点が取りやすい」と文系生に人気です。
ただし、思考問題やグラフ読み取りの出題もあるため、「なぜそうなるか」を意識して学ぶ癖**をつけることが重要です。
【対策法】
- 市販の共通テスト対応問題集(基礎からのジャンプアップノート、きめる!シリーズなど)を活用
- 教科書の図解や表をノートにまとめて視覚的に覚える
- 時間を測って演習し、50点×2=100点中70点以上を目指す
■ 基礎科目の“トラップ”に要注意
理科基礎は、「簡単そうに見えて時間が足りない」という受験生も多いです。
1問1問の資料が長く、処理に時間がかかる問題が含まれているため、試験慣れしていないと焦って失点します!
また、選択肢の文章が微妙にひっかけられていることもあるため、選択肢を丸暗記するのではなく、“根拠を持って選ぶ”意識を持ちましょう。
数学・理科が得点できると“本当に強い”
文系科目に比べて、数学や理科は「差がつきやすい」科目です!つまり、対策ができているかどうかで偏差値に大きく影響します。
たとえば、共通テストの国語や社会は平均点が60〜65点になることもありますが、数学や理科基礎は平均点が50点を下回ることも珍しくありません。
つまり、ちょっと頑張るだけで“平均超え”できる可能性が高い=周囲より有利に立てるということです。
理系科目は「避ける」ものではなく、「チャンス」に変えられるもの。
数学I・Aで70点、理科基礎で80点取れる文系生は、間違いなく“共通テスト型”の入試で有利に立てます。
まとめ:文系受験でも理系科目は武器になる!
最後に、今回のポイントをまとめましょう。
- 文系でも数学I・Aは原則必須。II・Bが必要な学部もある
- 理科は「基礎2科目」が主流。生物基礎+化学基礎が人気
- どちらも“完璧”ではなく“平均以上”を狙う戦略が有効
- 思考力・処理力をつければ、差がつく得点源になる
理系科目に苦手意識を持っている人も多いですが、裏を返せば「しっかり対策すれば差がつけられる分野」だとも言えます。
共通テストは全体の点数勝負。1教科で沈んでしまうと、他の得点が台無しになるリスクがあります。
だからこそ、文系でも理系科目は“避けずに向き合う”こと。
少しの工夫と努力で、数学と理科を味方に変え、合格にグッと近づけるはずです!