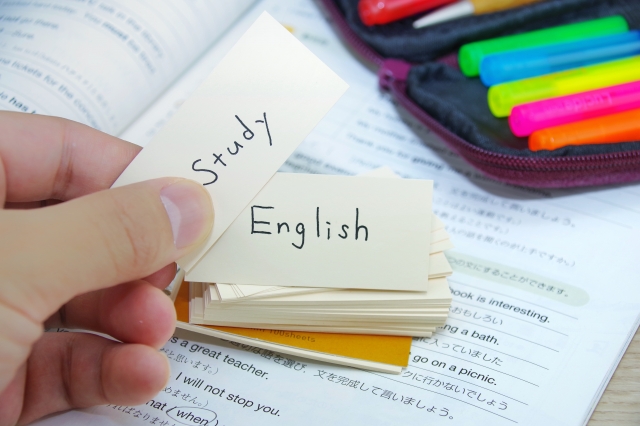はじめに
共通テストの英語リーディングは、センター試験時代の「文法・語彙中心」から大きく変化し、長文読解を通じて情報処理能力を試す試験へと進化しました。全てが長文で構成され、しかも設問形式も多様化。内容把握や要約力、情報の取捨選択が求められるため、「英単語は覚えたけど長文が苦手…」という受験生にはハードルが高く感じられます・・・!
しかし、出題傾向を理解し、効率的な練習を積めば、時間内に読み切って正確に答える力は確実に身につきます。そこで本記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、共通テストのリーディングで高得点を取るための具体的な勉強法と、本番で実践すべき戦略を解説します!
出題傾向を知ることが第一歩
長文化&情報量増加
共通テストでは、全体で約6,000語前後の英文が出題されます。センター試験よりも1.5倍以上の長さで、資料やメール、広告、記事など多彩な形式が混ざります。つまり、純粋な読解力だけでなく、複数の情報を照らし合わせて正答を導く力が必須です!
問われるのは「理解のスピード」
センター試験では設問の多くが単一の文章理解にとどまりましたが、共通テストは速読+精読の切り替えが重要になります。たとえば、本文の大意をつかむ場面では速読、設問の根拠を探す場面では精読といった具合です。

高得点を狙うための準備法
英単語・熟語の即時認識
リーディングでは、文章中の単語を「いちいち和訳して理解する」ような読み方では間に合いません。単語は見た瞬間に意味がわかるレベルにまで仕上げる必要があります。
目安として、共通テストレベルの英単語1,800〜2,000語は短期間で一周し、2〜3ヶ月かけて繰り返し定着させましょう。熟語も「make up for(埋め合わせる)」など文脈で意味が変わるものを押さえると有利です!
英文構造の把握
長文で迷子になる人の多くは、文の構造(SVO、修飾関係)をとらえられていません。日頃から短文の精読練習を行い、主語・動詞・目的語・修飾語の関係を瞬時に把握できるようにします。
過去問と類題で「形式慣れ」
共通テスト特有の設問(表やグラフと本文の照合、複数文書の比較など)は、解き慣れていないと時間がかかります。過去問や共通テスト対策問題集を使って設問形式に慣れておくことが重要です。
本番での時間配分戦略
大問ごとの時間目安
- 大問1〜2(短文・資料系):各5〜6分
- 大問3〜6(長文読解):各10〜12分
この配分で進めると、最後に5分程度の見直し時間を確保できます。途中でつまずいた場合は、迷ったら後回しを徹底し、1問に固執しないことが得点アップにつながります!
設問先読みの徹底
本文を読む前に必ず設問をざっと確認します。何が問われているかを把握してから読むことで、必要な情報だけを効率的に拾えます。
速読力を高めるための具体的トレーニング法
共通テストのリーディングでは、60分で6,000語前後の英文を読み切る必要があります。これは1分あたり約100語という計算になり、英語学習に慣れていない受験生にはかなりの負荷です。速読力を伸ばすには、単純に「たくさん読む」だけでなく、読みの質と目的意識を持った練習が不可欠です。以下の方法を組み合わせて、短期間でスピードと理解力を同時に鍛えましょう!
「時間制限付き精読」から始める
速読練習というと、ただひたすら早く読むことを思い浮かべるかもしれません。しかし、いきなりスピードを求めると、理解が置き去りになり、意味のない練習になります。
まずは1,000〜1,200語程度の英文を15〜18分で読み、内容を8割理解することを目標にします。読んだ後、内容要約を日本語で50〜100字程度でまとめると、理解度のチェックにもなります。
同じ文章を「繰り返し」読む
1回目は精読、2回目は理解を確認しながらやや早めに、3回目は制限時間をさらに短くして読む、と段階的に負荷を上げます。これにより、文章構造や頻出表現が頭に入り、次に新しい文章を読んだときの処理速度が上がります。
音読を活用して脳の処理速度を上げる
音読は視覚・聴覚・発声を同時に使うため、脳が英語を処理する回路を強化します。1日10〜15分で構いません。スクリプト付き音声教材を使い、スクリプトを見ながら音声を追いかける「オーバーラッピング」、音声なしで自分の声だけで読む「シャドーイング前の音読」を繰り返します。
スラッシュリーディングで意味のかたまりごとに理解
文章を前から順に意味のかたまりで区切って理解するスラッシュリーディングは、返り読みを防ぎ、自然と読解スピードを上げます。例えば:
I went to the library / to find some books / about environmental science.
このように、英語の語順のまま理解できる力を身につけることが速読への近道です。
長期的な目安設定
速読力は1〜2週間で劇的に伸びるものではありません。最低3ヶ月単位で計画を立て、毎週のWPM(Words Per Minute:1分間に読める語数)を計測しましょう。WPM120以上を安定して出せれば、共通テストの時間配分に十分対応できます。
複数文書を比較する問題の攻略法
共通テストのリーディングでは、複数の文章や資料を比較して答える設問が頻出です。メール、広告、ウェブサイト、記事など形式も多様で、しかもそれぞれの文章に似た情報が含まれていることもあります。このタイプの問題は、単一文書の読解よりも情報整理力が問われるため、対策なしでは時間を浪費しやすいです。ここでは、得点源に変えるための具体的な手順を紹介します!
「比較の軸」を先に把握する
問題文や設問を先読みし、何を比較するのかを明確にします。
例えば「2つのイベントの違い」を問うなら、日時・場所・参加条件・費用・特典など比較の軸を事前にリストアップしてから読むことで、本文中で必要な箇所を効率的に拾えます。
情報をメモや表で整理
複数文書を読む際は、頭の中だけで整理しようとすると混乱します。紙や余白に簡単な表を作り、項目ごとに情報を記入すると、設問への対応がスムーズになります。
例:
| 項目 | 文書A | 文書B |
|---|---|---|
| 開催日 | June 5 | June 12 |
| 費用 | $20 | Free |
| 参加条件 | 高校生以上 | 年齢制限なし |
情報の「一致」と「相違」を意識する
比較問題では、「両方に共通する情報」と「一方だけにある情報」を切り分けることが重要です。特に選択肢が「正しいものをすべて選べ」という形式の場合、情報の出所を正確に把握しておく必要があります。
誘導文や注釈に注意
複数文書の問題には、しばしば小さな注釈や補足情報が付いています。ここを読み飛ばすと、条件が変わってしまい誤答につながります。細部に目を配る意識を持つだけで正答率が大きく向上します。
過去問で形式慣れ
複数文書比較は独特の形式で、慣れていないと読む順番や比較の仕方で迷いがちです。過去問や予想問題を繰り返すことで、「設問先読み→比較軸把握→情報整理→選択肢検証」の流れが自動化され、本番でも迷いなく進められるようになります。



演習の際の注意点
「音読」と「黙読」を使い分ける
演習初期は音読を取り入れると、構文理解と語彙定着がスムーズになります。ただし本番は黙読なので、直前期は黙読速度を上げる練習にシフトしましょう。
復習で「なぜ間違えたか」を明確化
答え合わせの際、正誤だけでなく「根拠がどこにあったか」「なぜその選択肢を選んだのか」を振り返ります。この作業が次の演習での精度向上につながります。
まとめ
共通テストのリーディングは、「読むスピード」「情報の取捨選択」「設問対応力」の3つが鍵です。単語・熟語の基礎固めから始め、設問形式に慣れる練習を積み、時間配分を意識した演習を繰り返すことで、高得点は十分狙えます。本番では焦らず、準備してきた戦略を淡々と実行しましょう!
また、自習での対策に不安を抱く人はぜひ東大寺子屋をご活用ください!現役東大生の講師陣があなたのレベル・目標に合わせ共通テスト対策を行います。興味がある方はまずお気軽にお問い合わせください!